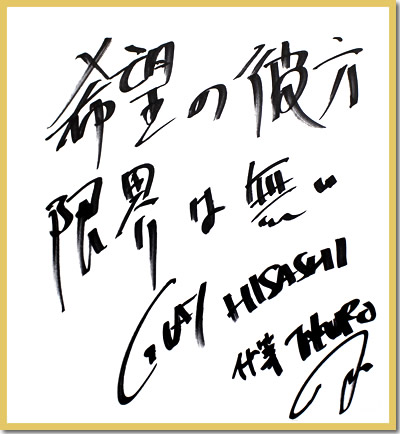―― 前回の取材でメンバー皆さんの歌詞の特徴をお伺いしたのですが、逆にGLAYとして音楽を作っていく上で似てくるところもあるのでしょうか。
未だにわりと近い生活圏内にいて会話も多いから、自分たちが今生きている時代の感じ方みたいなものは伝染している気がします。でも今回のEPでおもしろいなと思ったのが、僕は「Buddy」に<失ったものを数えるな>って書いたんですけど、逆にTERUは「刻は波のように」で<失ったものを探してる>って書いているんですよね。それぞれの人生に対する向かい方が表れているじゃないですか。
太陽みたいに明るいTERUだけど、普段は見せない心のうちにそういうものがあるのかと。俺のほうがある意味、乱暴で気楽だもんね。「失ったものなんて忘れて、前に行こうぜ!」みたいな。まぁ本人がどれぐらい曲と自分を重ねているかはわからないけれど、何十年付き合っていても、また新たな一面を見ることができるというか。おもしろい発見だなと思いましたね。
―― 今作のEPを作るにあたり、「失ったもの」をテーマにしようと話し合ったわけではなく、自然とおふたりとも同じものを異なる視点で見つめていたんですね。
不思議なことに。そういえばHISASHIの「Pianista」も<記憶の片隅のセピア>と歌っているし、喪失の歌ですね。実はそういうシンクロニシティってGLAYのなかでよくあって、それはなんでだろうと、ちょっと前にある本を読んだんですよ。学者・田坂広志さんの『死は存在しない』という本。量子科学から死に向き合った内容なんですけど、すごくおもしろくて。
簡単に言うと、人間は亡くなったら燃やされて灰になります。でも灰になっても、そのすべてがなくなったわけではなく、単に肉体が量子レベルまで小さくなっただけだと。つまり今までの動物から何から全部、まだ地球上にその物質はある。それが漂っている。そして、みなさんたまに誰かと何かがリンクすることってあるじゃないですか。「今まさにそれ言おうと思っていた」とか。それはもしかしたら、どこかに物質が付着したとき電流が流れて、目の前のひとが考えていることが伝わるのかもしれないらしくて。電気信号のバグというかね。
なるほどなと。長年のバンドとか夫婦とかが、言葉がなくても同じ方向を見ていたりするのは、そういう消えないものが漂っているなかでともに生きているからなのかと。
―― 一緒に過ごした時間のぶんだけ、同じ“何か”が量子レベルで付着している。
たとえばね「Winter,again」なんて、譜面を渡してみんなに弾いてもらったとき、最初はまったくイメージと違ったの。楽譜どおりなのに、なぜか違う。そこで、「11月の初雪が降る函館の桔梗町の国道線のあの感じ」って言ってみたら、「あ、なるほどね!」って同じフレーズを弾いて、もう明らかに音が弾んでいるのがわかった。それはきっと同じ景色を共有できていたからなんですよね。
ちょっと話は戻りますけど、そういう体験をしたからこそ、GLAYとして音楽を作っていく上でいちばん大切にすることは、音そのものが踊っているかどうかだなと思います。それがひとを感動させたり励ましたりする気がするから。最大の判断基準。悲しいラブソングであろうと、悲惨な戦争を歌ったものであろうと、俺らは“音が跳ねて命が宿ること” を伝えるバンドなのかもしれないですね。
―― その判断基準も言葉で伝えるわけではなく、4人がそれぞれ共有し合っているんですね。

そうですね。長い人生のなかで誰かひとりが落ち込んでいれば、そいつを励ますように演奏しようってそれぞれ意識する。それで曲の活き方が変わるわけです。ひとつの悲しい出来事があったとき、それを前向きに捉えても後ろ向きに捉えてもいい。だけどやっぱり大好きなひとがいつまでも落ち込んでいるのはツラいから、なるべく早く立ち直ってほしいという思いが音になって跳ねる。で、そういうまわりの気持ちに応えようとすることも、生きる上で大事だなと思うんですよ。そこはGLAYで音楽を作っていて強く感じますね。
―― 先ほどの「灰になっても消えることはない」話にも通じるかもしれませんが、今作の『HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P-』の「GHOST」というワードにはどのようにたどり着いたのでしょうか。
まさに、今まで隠れて見えなくなって、亡きもののように闇で蠢いていたけれど、たしかに今ここにあるGLAYの楽曲の声に耳を傾けようと。2023年がそういうコンセプトになったのはJIROの楽曲がきっかけでした。最初にJIROが「おもしろい曲を作ったから聴いてくれ」って言ったんですね。それで聴いたら、GLAYのDNAにはまったく入っていなかったダンスミュージックで、すごくおもしろいなと思ったし、感動したし、JIROからこんな曲が出てくる予想外の驚きもあったんですよ。
レコーディング準備のとき、俺はL.A.にいたんですけど、HISASHIとギターフレーズの打ち合わせの電話をして最後に、「ところでさぁ、今回4人4様で曲を出したけど、ぶっちぎりでJIRO優勝だよねぇ」って言ったら、「俺も思った。やられたよ」みたいな。そこから30周年前の今年のGLAYのコンセプトは、隠れた自分たちの曲を表に出してやろうという方向になり、JIROのあの曲に「THE GHOST」と名づけようと決まりました。
―― 「THE GHOST」の歌詞はTAKUROさんが手がけられていますね。
実はもともと俺が「GHOST」という曲を別で書いていたんですよ。歌詞の内容はこんな感じ。だけどJIROの曲のほうが絶対に活きるなと思って、俺の曲はボツにして、歌詞だけ持ってきて手直ししました。なんかね…今年のGLAYはまったく世の中に知られてない曲ばかりやります。もちろんキャリアのあるバンドで、ヒット曲を中心に年に一度の同窓会みたいなライブをやるのも魅力的だし、俺もよく行くの。でも一方で俺は、そういう音楽業界の狭さのようなものに窮屈な思いもあってね。
エンターテインメントの世界を見渡せば、小説も映画も漫画もどんな結末かわからないことを楽しむじゃないですか。だけどなぜかキャリアを積んだバンドは、みんなが知っている曲をやらないと、「今日のライブは知らない曲ばかりだった」とネガティブな感じで言われてしまう。そうやって「つまらない」と切り捨てるのは簡単だけれども、でももしあなたが「つまらない」と思ったのなら、TERUの指揮のもと、ちょっとステップを踏んでごらんと。腕もあげてごらん。ドラムのキックを感じて、それに合わせて肩を揺らしてごらんと。
するとエンターテインメントを楽しもうという内なる気持ちがどんどん沸いてきて、自分で自分の機嫌が取れる気がするんですよ。お客さんもアーティストも共犯になったら、ライブはもっともっと盛り上がるはず。「どう楽しませてくれるんだ」「あなたのせいだ」という態度ではない生き方によって、十二分に楽しいショーになることをGLAYが証明したいという気持ちが今ありますね。
―― 1曲目「Buddy」もまさにイントロから自然と心も体も踊るような曲ですね。どのように生まれた楽曲なのでしょうか。
これはうちの近所のレストランと俺の大好きな芸人さんたちの歌なんですよ。まずよく行くレストランは、歌詞のとおり2人でやっているんですね。厨房のシェフがひとり。フロアにひとり。楽しい連中で、店立ち上げの苦労話なんかも聞いたんだけど、「もうそのまま歌詞じゃん!」と思ったんだよね。
あと、コロナ禍でしんどい頃にJIROがよく、「テレビをつけるとコロナのニュースばかりで落ち込んじゃうから、お笑い芸人さんのラジオを聞いているんだよね」と言っていて。俺も教えてもらって、そこからいろいろ聞くようになったんですけど、彼らは本当に楽しいことばかり話してくれる。それにとっても救われて。だんだんもっと興味を持つようになって、ライブに行ったりもするようになってね。
そんななかで、お笑い芸人さんのコンビの関係ってめちゃめちゃおもしろいなと。もう「Buddy」としか言いようがない。たとえばニューヨークの出した本を読んだり、ナイツから話を聞いたりすると、お笑いってM-1とかキングオブコントとか、ある種の競争の世界でもあって。一夜にしてスターになるジャパニーズドリームを地で行く世界じゃないですか。その道をバディーとして進んでいくお笑いコンビの在り方によって、あのレストランの物語にもさらに磨きがかかるなと。2つのきっかけから歌詞が生まれた感じですね。
―― 「Buddy」の歌詞は苦労話の愚痴というより、そのとき<オマエ>がどう在ってくれたか、どれだけ<オマエ>に感謝しているかの想いが溢れていると感じました。
とくにお笑いのひとたちって息が長いじゃないですか。50代、60代でもベテランのコンビが多い。そうなってくるともう本当に<分け合った時間は何よりも尊いね>というようなかけがえない気持ちを感じるみたいで。だからといって、距離は縮まりもしないし離れもしない。その絶妙な感じがいいんですよ。音楽業界の2人組なんかも「Buddy」感がありますよね。PUFFYにしても、B’zにしても。逆にGLAYは距離感がバグっているじゃないですか(笑)。だからこそ「Buddy」って独特で、ちょっと憧れるなって思いますね。